自転車徘徊紀行(第38話)高低差ほぼ0メートルのコースをパスハンターで走る
40年以上前になるだろうか、峠超えサイクリングに特化した「パスハンター」と呼ばれる車種が流行した。
パスハンターは小旅行車であるランドナーをベースに、長い登りに適したギア比や乗車ポジションになるように考慮したもので、担ぎも考慮してフレームポンプやボトルゲージの位置を工夫したり、作り手の考えと経験が盛り込まれた個性豊かな自転車たちは、見るだけで面白かった。
パスハンターはマスプロメーカーのブリジストンも発売するなど、マウンテンバイク到来前に盛り上がりを見せたが、アルプス自転車工業が販売していた「クライマーシリーズ」は当時の峠を目指す多くのサイクリストの憧れの的ではなかったろうか。
当時学生だった私も例に漏れず、雑誌の中のクライマーシリーズの写真を飽きもせず眺めていたものである。
社会人になって、初めて本格的な自転車を注文するとき、クライマーにしようかとかなり悩んだ。
結局は予算との兼ね合いもあって、登坂優先仕様のランドナーを付き合いのあるショップにオーダーした。
それが、本紀行の第36話で紹介したランドナーで、ポタリング専用車になりながらも今でも動いている。
それでも、クライマーをあきらめきれずに、20数年前、最上位機種であるスーパークライマーの購入を決断した。
当時、にわか仕込みの部品知識をもとにヤフオクで集めたような幾つかのパーツを使って組んでもらおうと考えた。
アルプスと言えば、輪行を考慮したサンプレックス社のリアディレイラーを使用している印象があったが、既にフランスパーツはほぼ絶滅状態の時期で、シマノのデュラエースのメカが標準装備だった。
実用面を第一に考えて、デュラエースのままにしておけば良いものを、私はユーレー社のドッパーを持ち込みで組付けてもらうようお願いしたのだった。
ドッパーはとても独創的で魅力的なメカ構造をしており、驚異のワイドレシオを誇っていたが、パスハンターに使うには必要以上にワイドレシオで重量があり、実走を優先すれば普通は行わない選択だった。
あこがれのアルプスを訪問し、直接オーダーしたのだが、もともとサンプレックス派の店長に、ユーレーのドッパーのアッセンブルをお願いするとは、今思えば浅い知識の田舎者と思われたであろう。
完成したとき、とてもうれしかったが、ドッパーのリアディレイラーは倫行の際、外に大きく出っ張るので、どこかにぶつけたら簡単に壊れそうで、選択を少し後悔した。
それからまもなく、登坂中の変速の際、チェンを巻き込んでドッパーのゲージがひん曲がってしまい、交換する羽目になった。
下手に自分好みの部品を選ぶのではなく、経験豊かなアルプスの標準仕様のパーツアセンブルにすべきだったと思ったが後の祭りだ。
私がスーパークライマーを購入した数年後に、アルプス自転車工業は惜しまれつつ閉店してしまう。
購入が間に合って良かったという思いと同時に、あこがれ続けたアルプスが無くなったのはとても寂しい気持ちになった。

さて、そのスーパークライマーだが、最近ではほとんどこれに乗っている。
しかし、峠越えとは言えないせいぜい200~300m程の山越えのポタリングコースを走る程度になってしまった。
日によっては、ひたすら平らな干拓地の防潮堤コースだ。
ただ、アルプスのカタログのクライマーシリーズの説明では、峠越えだけでなく低速でのんびりと散歩するにも適しているという主旨のことが書いてあり、使い方がおかしいわけではない。
つまり、林道の登りなどを考慮して、フレームスケルトンが低速で安定する設計になっており、それはのんびりと走るポタリングにも適しているということなのだ。

そろそろ、スーパークライマーで、阿蘇や五家荘の山岳コースを走らねばと思いつつも、これらのコースと対極の高低差ゼロのコースを、しかも、実にのんびりと走ることに甘んじている毎日なのです。


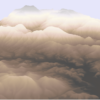




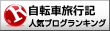
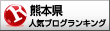
最近のコメント